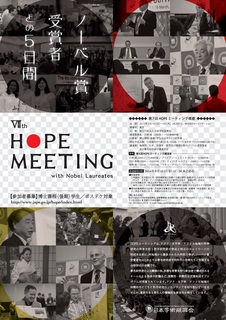書評
獣医学教育モデル・コア・カリキュラム準拠
獣医遺伝育種学
国枝哲夫・今川和彦・鈴木勝士 編集
発行/2014年5月25日
ISBN978-4-254-46033-9
朝倉書店 定価/本体3800円+税
本書は獣医学教育モデル・コア・カリキュラム(同カリキュラムに関する調査研究委員会編集、平成23年版)に準拠して編集された動物遺伝育種学の教科書であるが、新しいゲノム研究成果を踏まえ、ゲノムー遺伝学-育種学-遺伝性疾患を体系化したものである。獣医学の学生のみならず、応用動物科学系(畜産系)の学生、研究者、技術者及び行政の担当者にもお勧めしたい教科書である。
獣医学教育モデル・コア・カリキュラムとは「獣医学生が大学卒業時までに身につける必要不可欠な知識と精選した教育内容のガイドラインであって、具体的な到達目標を明示することによって分野ごとの教育内容とレベルを確保することを目的として」「獣医学として教えるべき3分の2程度の内容」を示したものである。なお、残りの3分の1の内容については各大学において充実強化されることが推奨されている。導入教育・基礎獣医学教育分野13科目、病態獣医学教育分野7科目、応用獣医学教育分野8科目、臨床獣医学教育分野23科目が講義科目として並んでいるが、導入教育・基礎獣医学教育分野13科目の1つとして動物遺伝育種学がある。動物遺伝育種学では全体目標の下に6項目(遺伝様式の基礎Ⅰ、Ⅱ、遺伝的改良の基礎、質的形質の遺伝、応用分子遺伝学とその実践、動物の遺伝性疾患)が、一般目標と到達目標とともに述べられている。
本書をみると演習問題を含め、動物遺伝育種学モデル・コア・カリキュラムのガイドラインの構成にほぼ忠実に沿って編集されていることがわかるが、これを具体化した編者・著者の意欲的な取り組みを高く評価したい。
一方、本書を細かく読むと、編者の独自性も推察される。すなわち、第3章と第4章の順番が逆転し、第6章家畜の品種と遺伝的多様性が追加され、動物の遺伝性疾患が概論(第7章)と各論(第8章)に分けて記述されている。これは各大学で独自に追加すべき3分の1の内容を意識して編集した結果とも推察される。そして、うがった見方をすると本の表題を「動物遺伝育種学」ではなく「獣医遺伝育種学」にしたことに編者らの独自の考えがあるのではないかと推察される。
獣医学教育モデル・コア・カリキュラムでは動物遺伝育種学は導入・獣医学基礎科目1単位の科目として位置付けられ、実習科目には含まれていない。一方、畜産学においては教育モデル・コア・カリキュラムのような統一基準は設定されておらず、カリキュラムは各大学の独自性にまかされている。しかし動物遺伝育種学は畜産学の基幹科目2単位であり、関連科目もあり、更に実習も大きなウエイトを占めている。これが多くの大学の畜産学に共通した考えである。また、畜産学で使われている動物遺伝育種学の教科書においては、個体よりも集団、質的形質よりも量的形質に重点がおかれ、遺伝性疾患は淘汰すべき形質として扱われている。畜産学では動物遺伝育種学分野の大学院への進学者も多く、畜産行政を担う人材の養成部門ともなっている。私は畜産学の教育研究の充実は畜産のみならず獣医学における動物遺伝育種学の3分の1の内容の強化をもたらすと考える。本書には畜産学との共存が獣医学強化につながるとの考えが反映しているように思われる。すなわち本書が動物遺伝育種学ではなく獣医遺伝育種学とされたのは畜産学への期待があるからではないかと推察される。
改めて畜産学分野の動物遺伝育種学の教科書を検索してみたが、基幹科目であるにもかかわらず出版数は意外に少ない。すぐれた教科書があって、初めて当該分野の教育研究は定着し発展すると思われる。本書は5名の優れた動物遺伝育種学分野の研究者によって執筆されている。どちらかというと獣医学よりも畜産学に基盤をもつ研究者が多い。本書を執筆された方々が中心となっての畜産学分野での教科書出版に期待したい。それぞれの研究者が自らの考えを簡潔に次世代向けに表現し、多くの研究者の目に曝され、批判を受けることが動物遺伝育種学の展開に必須である。また、そのことが獣医学において各大学の努力によって追加されるべき3分の1の講義内容をより充実することにつながると考える。
動物の遺伝性疾患の各論を読むと産業動物では、遺伝性疾患の診断法の確立、キャリアの同定で終わり、淘汰を前提として記述されている。伴侶動物でも遺伝性疾患の診断法、キャリアの同定が述べられているが、遺伝性疾患の診断の進んだ血友病、ムコ多糖症では遺伝性疾患の多様性や治療法が述べられている。すなわち伴侶動物では遺伝性疾患を淘汰ではなく治療の対象として取り扱っている。
ゲノム研究の進んだヒトでは胎児の遺伝子診断のみならず、受精卵の遺伝子診断も行われるようになり、堕胎や胚の選別・移植も可能となり、その是非について議論が活発化している。遺伝性疾患の診断が進めば、伴侶動物においては再生医療や遺伝子治療も課題になるだろう。どのような遺伝性疾患を動物集団から排除するか、どのような遺伝性疾病をどのような治療によって助けるのか、などの議論が発生するに違いない。個体の遺伝子改変が究極の遺伝子治療として登場するかもしれない。
遺伝性疾患を淘汰すべきか、治療すべきか、遺伝子改変による治療を認めるかなどについてどのように講義するかは当然ながら今のところ共通認識はない。教える側の考えが問われる問題である。このような点も各大学の判断で独自に追加すべき3分の1に含まれるだろう。また、獣医学教育モデル・コア・カリキュラムには倫理学の講義科目はないが、獣医遺伝育種学の進展により、例えば「獣医医療倫理学」などの科目の追加も考える必要がでてくるのではないかと予想される。
いずれにしても話題豊富な教科書の出版である。
(佐藤 英明 会員)