 |
| 写真1 UCSD La Jolla キャンパスにあるBasic
Science Building 手前にあるような美術品がキャンパスのいたるところに見られる。 |
私は2003年4月より1年間、Department of Reproductive Medicine, University of California San Diego (UCSD), School of MedicineにPostdoctoral Researcher (ポスドク)として留学の機会を得る事ができました。
パドレスというメジャーリーグチームに所属する日本人選手のお陰で、最近サンディエゴの認知度が高くなっているのではないかと思います。しかし、チャージャーズというアメリカンフットボールチームの存在を知る人は少ないでしょう。ましてやチームのチアリーダーであるチャージャーガールに日本人女性が活躍していることを知っているのは住んでいる人だけではないでしょうか。
このサンディエゴは全米で7番目(カリフォルニア州で2番目)の規模のメキシコとの国境に位置する都市です。The finest cityと呼ばれるこの街は、気候も1年中穏やかで非常に住みやすく、至る所に植えられたパームツリーや色とりどりの草花、空の青さといい、映画やテレビの中に入り込んだのではと思うほどでした。とりわけ、あの雪中行軍で有名な八甲田山の麓に位置する、十和田から転居した私にとって非常にギャップの大きいものでした。
また、UCSDを中心にSalk Instituteなどの研究所や製薬会社、ベンチャー企業などがサンディエゴに集まって、そのBiotech and high-tech hubとしての発展は目覚ましいものがあり、Nature誌 (vol. 426, No. 6967, 2003)にも取り上げられています。
これらの大学や企業、研究所に所属する日本人も数多く、日本人コミュニテーも発達しています。そのためか、日本車や「Sushi」は勿論のこと「Tofu」「Daikon」「Koi(錦鯉)」といったように日本文化が意外にも浸透しており、時折とても驚かされました。
さて、私が在籍したのは、Shunichi Shimasaki研究室です。その名の通り日本人Principal investigator (PI)です。それまで、Dr. Shimasakiとは面識はありませんでしたが、私が以前お世話になった教授との関係からアクチビン・フォリスタチン関連の共著論文が2本ありました。2002年秋に東京で開催された、あるシンポジウムで先生とお会いし私の研究内容を説明した際に「Goalは?」「Speedは?」というDr. Shimasakiからの質問に、心を打たれたのが留学するきっかけとなりました。なぜなら、学生の「卒論」のためだけの実験になりかねない研究環境にいる私にとって、非常に魅力ある言葉だったからです。また、アメリカでPIとしてラボを構える日本人にも興味がありました。
このDr. ShimasakiはSalkやScripps Instituteなどに在籍経験があり、約20年間アメリカにおいて活躍されています。その間、アクチビン・フォリスタチンやIGFBPなどの単離やクローニングに大きく貢献してきました。UCSDには1997年にprofessor (tenured)として就任以来、TGF-β super familyに属する因子であるBone morphogenetic protein (BMP)、特に卵子特異的に発現しているBMP-15の機能をgranulosa cell 培養系等を用いて解析しています。その成果はEndocrine Reviews誌 (25:72-99, 2004)の表紙を飾るほどです。
BMP-15遺伝子のミュータントヒツジでは排卵数が増加することから、BMP-15の排卵数調節への関与が考えられています。また、TGF-β super familyの因子は種々の動物種間でそのアミノ酸配列は90-100%と良く保存されていますが、例外的にBMP-15は約70%しかありません。そこで、私は、BMP-15が排卵数調節因子であるという証拠をつかむために、単排卵動物であるヒトBMP-15と多排卵動物であるマウスBMP-15の機能を、組み換え蛋白やトランスジェニックマウスを用いて比較する、というプロジェクトに参加しました。
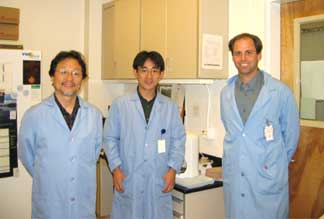 |
| 写真2 ラボコートを着込んで動物施設に向かうところ 左から、島崎俊一先生、筆者、R. Kelly Moore(サンディエゴ出身 postdoc. シュンイチの右腕的存在。彼には研究面のみならず生活面でも大変お世話になった。) |
研究室のメンバーは、秘書1人、ポスドク4-5人、大学院生1人、テクニシャン1人、出身国はアメリカ、中国、インド、韓国、シンガポールとやはり多国籍でありました。
そんな環境の中で下手な英語を使いコミュニケーションをとり、実験をして良いデータを出し、ボスや仲間の信頼を得ていくのは容易なものではありませんでした。渡米直後は、英語で言いたいことも言えず、話しかけられても聞き取れず、非常に落ち込む毎日を過ごしていました。また、アパートや電気、水道、ガスの契約など生活面での苦労や失敗談など枚挙にいとまがありません。しかし、これらのストレスや後述するストレスはカリフォルニアの青空のもと週末に家族で出かけるSan Diego ZooやSea Worldなどへ遊びに行く事によって解消されます。アメリカでは人生を楽しんだり、家族に対するケアのためにほとんどの土日や祝祭日を費やしているようです。(そのために非常に効率良く働いています。) 昼食時の話題は、毎週水曜日には今週末の計画で、月曜日にはその報告でした。これは義務づけられているのではないかと言うくらいのものでした。時折、我々も強迫観念にかられて、無理して遊びに行き、非常につらい月曜日を迎える事もありました。
再びDr. Shimasakiの話にもどします。彼とのコミュニケーションには日本語は禁止で、さらに、私に限らず「Dr. Shimasaki」という呼びかけも禁止で「シュンイチ」とファーストネームを使わなければいけなかったことには、まさしく閉口しました。しかし、これはたとえ生活面でも、何かあったら何時でも気軽に相談しなさいという、ポスドクや学生に対するサインであると思われます。しかし、研究に対する姿勢は非常にシビアで我々ポスドクは高い生産性を求められます。これはシュンイチに限らないことだと思います。なぜならPIはポスドクが出したデータをもとに多額のグラントを獲得し、その中から、研究費、ポスドクの給料さらには自分の給料まで捻出しなければならないこともあるからです。
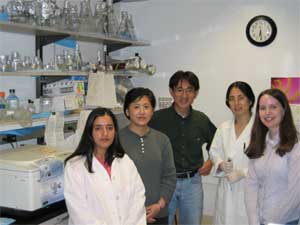 |
| 写真3 研究室での記念写真 左から、 Shweta Sharma(インド出身postdoc. 彼女の研究に対する貪欲さは見習うべきものがある)、Mei Wang(中国(カナダ国籍)出身 lab. assist. 岡崎基礎生物学研究所でテクニシャンの経験を持つ)、著者、Xia Wang(中国出身 postdoc. 山形大学医学部で学位を取得した)、Heather McMahon(ワシントン州出身 Ph.D. Student 良くトレーニングされており、将来が楽しみである。) |
我々ポスドクは、だいたい月に一度順番が回ってくるラボミーティングにおいて、それぞれの研究テーマ内で得たデータを発表するのが義務づけられています。これはポスドクにとって生き残りをかけたとても大事な舞台であり、ここでボスのお眼鏡に叶ったデータを出すために日々実験をしている、と言っても過言ではない状況も生まれます。いずれにせよ、ボスや同僚からよせられる信頼や契約更新、サラリーにも響いてくるため非常にストレスのかかるものです。しかし例え、良いデータが得られなかったとしても、シュンイチの経験、知識に基づいたデータの読み方や手技の確認、軌道修正など色々な指示やアドバイスを得ることが出来ます。
アメリカの研究現場には数多くの日本人研究者が活躍しています。それはあたかも、アメリカに高性能で燃費の良い日本車が溢れているかのようです。穿った見方をすると「日本には帰りたくなくなるような研究環境が存在する。」という事かも知れません。蛋白質核酸酵素(49: 697. 2004)に興味深い記事が掲載されていました。
確かに何でも合理的なアメリカのシステムが必ずしも良いとは言えませんが、日本の研究レベルをあげるために、積極的にアメリカのシステムを取り入れ改善していかなければいけないのではないでしょうか。そのために、シュンイチのような研究者に日本に帰国していただき、そのノウハウを生かしていただきたいと願います。
最後に、この場をおかりしまして、留学中ご迷惑をおかけした北里大学獣医畜産学部の皆様、留学中お世話になったDr. ShimasakiをはじめとするUCSDの皆様、サンディエゴでお世話になった皆様、遥々サンディエゴまで激励に来ていただいた諸先生、私の都合で引きずり回してしまった妻子に感謝いたします。