
Ron Christenson 博士(共同研究者)、
USDAのstaffと今川助教授

今井美沙(修士2年)



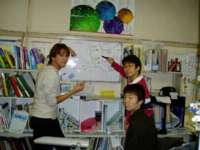


| 研究室紹介
東京大学大学院農学生命科学研究科・獣医学専攻 |
【JRD2003年12月号(vol.49, No.6)掲載】
私たち東京大学大学院農学生命科学研究科・獣医学専攻の着床研究グループ(今川和彦助教授)は動物育種繁殖学研究室(酒井仙吉教授)にて、「世界へ発信する研究を行おう」という目標を掲げ、少数精鋭で研究を行っています。そのため、個々の研究者(学生)は次の3つの項目が常に要求されます。
★Determination …“自分がよい研究をしたい”ことや“自分の(研究)作品を世に出したい”というハングリー精神を持ちつづけること。高い志なくしては世界に羽ばたく研究はできない。
★Teamwork …個々の人間ができることは非常に限られている。お互いに助け合い補い合うことでScienceにおける人間関係を築き上げ、切磋琢磨することで全体の研究のレベルを相乗的に向上させていく。
★Intuition & Serendipity …自己の能力を信じきれるか? Scienceの世界で自ら生き抜いていく意志や能力、才能の有無、研究に対する適正を見極めたい人には最適な研究室であると考えています。
|
1 今川助教授
|
 |
|
2 米国農務省の
Ron Christenson 博士(共同研究者)、 USDAのstaffと今川助教授 |
 |
|
3 今川助教授、Ron
Christenson博士、
今井美沙(修士2年) |
 |
|
4 ヒツジの妊娠子宮と胚
|
 |
|
5 米国農務省の牧場とヒツジ
|
 |
|
ディスカッションおよび実験風景
|
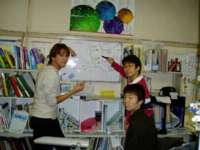 |
 |
 |
着床研究グループの構成員は、五十鈴川和人(ポスドク)、今井美沙(修士2年)、秦 俊文(修士1年)、山本慎也(獣医5年)、飯塚真央(獣医4年)、研究生の小寺敏晴と指導教官の今川和彦(助教授)からなる7人の“サムライ”である。この他に、共同研究者及びテクニカルアドバイザーとして夜な夜な教えに来てくれる成育医療センターの高橋裕司博士がいる。学生数を増やさないのは、少数の研究者志望の人材をリソースと時間をかけて鍛えていこうとする考えからである。事実、毎年4月1日より一日一時間(日曜日を除く)で約2ヵ月半、新規入室者に研究の「イロハ」や論文の選び方、読み方とその利用方法、「仮説」の立て方やその証明法などマンツーマンの指導を行っている。
■研究紹介
生物は種特有の生殖方法により、自らの子孫を残すように進化してきた。特に哺乳類は無性生殖で増殖する下等動物とは異なり、有性生殖、とくに着床、胎盤形成を特徴とする"妊娠"という特有の生殖形態を作り出した。哺乳類の妊娠は受精、卵割、透明帯からの孵化、着床、胎盤形成、妊娠の維持、胎児の発育、分娩といった一連の過程からなり、誕生までに至る個体はこれら全ての関門を通過したものに限られる。
ヒトの体外受精(IVF)の妊娠率は約20%でありここ10数年変わっていない。また、産業動物の領域でも受精卵・初期胚の約半数は着床の完成(初期胎盤の形成)までに至らず死滅してしまう。この事実は何を示しているのだろうか?受精卵にはもともと不完全なものが多く、初期胚の発達段階の初期に異常が現れるのだろうか?それとも、異常がないにも関わらず着床過程のなかで致死になってしまうのだろうか?初期胚は何故、母親からもらった透明帯を脱ぎ捨てて(孵化)から着床過程に移行するのだろうか?母親は胎児を自分の物ではない「異種タンパク」として認識し抗体を産生しているのにも関わらず「通常」は免疫学的に排除することはない。さらに、遺伝的変異により、妊娠が必然的に成立しない、あるいは維持されない状態を胎生致死といい、近年の遺伝子ノックアウトマウスの作出により、この表現型を示す遺伝子が次第に同定されてきている。これらの遺伝子がコードするタンパク質の機能を解析することで、謎に包まれた「妊娠」という現象に細胞生物学的、分子生物学的、そして生化学的な説明を付加することが可能になると考えられる。いずれにしても、「着床や妊娠の成立」という生命現象にはいまでも解決されていない問題が山積している。我々の「着床」を中心とした研究は、主に以下の研究領域のなかで一人ほぼ一研究領域を担当している。
1.遺伝子欠損マウスを用いたHβ58遺伝子の機能解析
Hβ58(Vps26)は、ランダムな遺伝子ノックアウト法(insertional mutation法)を用いて発見されたタンパク質であり、この遺伝子欠損胚は胎齢11.5日目までに胎生致死に陥る。このタンパク質は細胞内タンパク輸送に関与すると考えられているが、不明な点が多く、それ以上に胚が死に至る原因が全く特定されていない。Hβ58(Vps26)は酵母からヒトに至るまで保存されており共通の機能を持っていると考えられるが、酵母の遺伝子欠損株は生存し、正常に分裂を続ける。我々はこの点に着目し、この分子の正確な機能(輸送先、運搬するタンパク質、複合体の形成 etc.)を知ることで、実際にこのタンパク質を持たない哺乳類(マウス)細胞でどのような変化が起こっているのかを解析中である。
さらにノックアウトマウスを用いてin vivo、in uteroで実際に何が起こっているのかを明らかし、最終的には妊娠(胎生致死)と細胞内輸送という2つの分野の統合を目的に研究している。2.マウスの着床に関与する遺伝子の探索
着床とは胚が母体に接着、浸潤し、胎盤原基の形成を行うという一連の過程を指し、哺乳類の妊娠にとって非常に重要な現象である。着床に関与すると考えられる分子はいくつも報告されているが、現在の知見を基にするだけでは、この現象の全貌を明らかにすることができない。特に着床期の初期胚は母体との間で複雑かつ綿密なコミュニケーションをとっていると考えられ、これらの胚−母体間情報伝達を担っている分子を探索することで「着床」をこれまでとは違った観点から見ることが可能となる。
当研究室では着床をin vitroで再現する実験系を組み立て、DNA microarray法を用いて、母体や胚で着床期に発現が変化する分子の網羅的解析を行った。その結果、ストレスや(ガン)細胞増殖抑制遺伝子群など、これまで着床に関与すると考えられていなかった遺伝子群に発現の変化が見られた。
現在はDNA microarrayの結果をもとに、これらの中から細胞の分化・増殖などに関与するとされるacrogranin、epimorphinの着床における役割を、in vivo及びin vitroの実験系を用いて解析している。3.反芻類着床期におけるケモカインの役割
着床とは異種細胞同士(胚のトロホブラスト細胞と母親の子宮上皮細胞)が接着、融合あるいは浸潤をしていく現象である。胚のトロホブラスト細胞で発現する遺伝子群には父方由来(ゲノミックインプリンティング)ものが多いことが知られている。この免疫学的に矛盾(?)する遺伝子発現は何を意味するのであろうか?反芻動物において着床期の胚より特異的に発現されるインターフェロン・タウ(IFNτ)が妊娠の成立に深く関与することが知られている。今までの実験結果より、胚から発現されるIFNτにより着床期特異的に子宮側よりケモカインIP-10の発現が誘導されることが分かっている。ケモカインにはもともと血液細胞を誘導あるいは集合させる働きがあるので、胚自身が母親の免疫反応に関与あるいは制御している可能性が出てきた。一方、子宮側から発現するIP-10が、胚側に存在するCXCR3レセプターを介して胚を子宮側に呼び寄せ、着床を誘導するのではないか(仮説)と考えるようになった。胚が着床するには子宮上皮との接着が必要であり、これにはインテグリンなどの接着分子が関与していると思われる。そこで着床期に特異的に発現するインテグリンを同定し、その後胚がどのように子宮側に浸潤するのかをin vitroやin vivo実験系を活用しながら解明しようとしている。4.Interferonτ−現在と未来
ヒトやマウスを初めとする哺乳類の受精卵は卵分割を繰り返しながら子宮に到着する。そこでブラストシストまでに発達した胚は、透明帯を脱ぎ捨てた後、種特有の方法によって母親に妊娠を認識させる。このシグナルを受けて母親は受け入れ(着床ウインドウ)態勢を整えるために、胚は着床過程(接着・浸潤・初期胎盤形成)へと進むことができる。そして、着床した胚のみが妊娠の成立すなわち生命体として生存しうる保障を獲得するが、通常、約50%の胚仔がこの時点で死に至ってしまう。
反芻動物のウシやヒツジの胚栄養芽細胞から分泌される(IFNτ)は母体の子宮内膜層に働き、黄体退行因子であるプロスタグランジン(主にPGF2α)を抑制することが知られている。その結果、母親の卵巣に存在する黄体は形態的にも機能的にも維持され、妊娠ホルモン・プロジェステロンの分泌が維持される。この現象そのものは30年以上前に知られており、「母親の妊娠認識」と呼ばれている。この後、子宮は胚の受け入れ(着床)に向けての準備を始め、一定の時間(着床ウインドウ)のみ胚仔を受け入れることが分かっている。しかし、妊娠認識のマーカー因子ばかりではなくメカニズムも未だに解明されていない。そこで、胚IFNτの機能および遺伝子発現制御機構を明らかにするとともに、胚IFNτによる母体側の遺伝子発現制御機構と着床過程における子宮−胚間の相互作用を分子レベルで明らかにする。また、体細胞クローンを含む体外受精や顕微授精によって作出された胚が分泌するIFNτの発現時期や発現量を検証する。そして、これらの胚の低い着床率とIFNτのシグナル伝達やIFNτによって制御されている着床関連遺伝子群の発現制御などの関連性を明らかにし、着床率や胚生存率の向上技術を確立していく。5.ヒト・クローン病
2年前、獣医薬理学教室の尾崎・堀両先生と立ち上げた共同研究であり、主にトランスクリプトームやプロテオーム解析から、病態進行制御のための遺伝子(群)の同定と血清タンパク中のマーカータンパク(因子)の探索を行っている。この研究から得られる知見は近い将来、クローン病だけではなく、着床とくに胎児胎盤と子宮脱落膜との関係を炎症反応という新しい視点に立って解析していくための基礎データとなることが期待されている。
■おわりに
若者には限りないポテンシャルがあると信じています。しかし、そのポテンシャルも使わなかったら、いつまでもポテンシャルにすぎません。中には、ポテンシャルを目いっぱい使うのではなく、適当に使いながら生きようとするヒトも大勢います。「そのどちらが良いのか」、または「どちらを選ぶのか」は誰にも判断できません。問題は「自分」が「どれを選択して生きるか」です。研究は万人のものでもなく、また(他の職種でもあるように)誰もが成功するわけではありません。しかし、様々な生命現象に興味をもち、未解決部分を見(嗅ぎ)分けることができ、それを解明しようとするヒトにとってはこれほど魅力のある領域はありません。生命現象の中では、まだまだ未解決な現象が山積みしています。それから目をそらすのも、探したいと考えるのも、また実際に探すのもあなた自身なのです。
つまり、”You don't have to prove anything to anyone, but to yourself.”なのです。もうすぐ、ホームページが立ち上がります。
This site has been maintained by the JSAR Public Affairs Committee.
Copyright![]() 1999-2003
by the Japanese Society of Animal Reproduction
1999-2003
by the Japanese Society of Animal Reproduction