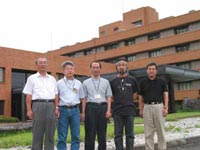
発生分化研究チーム長

池の台地区案内板
| 施設紹介
独立行政法人 居在家義昭 |
【JRD2003年8月号(Vol. 49, No. 4)掲載】
■はじめに
筑波研究学園都市にある独立行政法人農業生物資源研究所は、旧農業生物資源研究所、蚕糸昆虫農業技術研究所、畜産試験場の一部、家畜衛生試験場の一部の分野を研究主体として、平成13年に出発しました。職員数は約400名を超え、14部門の研究グループからなる大きな組織です。キャンパスは学園都市内でも5カ所に分散していますので、電子メールだけに依存しない、コミュニケーションの確保には苦心するところです。本研究所の主体はゲノム、遺伝子機能解析を主とする植物と昆虫(蚕)の研究ですが、家畜を対象としている研究者も約45名が配置されています。
発生分化研究グループは6研究チームから構成されています。職員数は24名ですが、ポスドクや非常勤職員等を含めると約70名近くの所帯となります。独立行政法人畜産草地研究所内の池の台キャンパスには分化機構、発生制御、発生工学、生殖再生の4研究チームが、約5
km離れた大わしキャンパスには発生機構と成長制御研究チームが設置されています。これまでの歴史的経過から、池の台キャンパスでは家畜(動物)、大わしキャンパスでは昆虫を主体とした研究の展開を図っています。従来の研究区分からは考えられない異分野共同体としてのグループですが、それぞれの特徴を活かしたユニークなものが出せればいいと期待をしています。グループ員一堂が介する機会もなかなか設けられないのですが、定期ゼミや親睦会などで、できるだけ交流を図るようにしています。
■研究概要
当グループの研究理念は、「家畜の特性を理解し、健全な家畜を創るための研究」および「動物の新規利用のための研究」を基本とする、動物生命科学を樹立することにあります。
分化機構チームは、マウスをモデル系としたES細胞等の増殖・分化制御要因の解析に取り組んでいます。細胞表面マーカー抗体の発現状況とキメラ形成能との関連、多分化能維持に必要な発現遺伝子の解析を行っています。さらに、体細胞クローンを利用した形質転換ヤギの作出による有用物質の生産系の確立も重要なテーマの一つとなっています。
発生制御研究チームでは先駆的に確立した家禽胚の卵殻外ふ化技術を基礎として、個体再生が可能な始源生殖細胞や胚盤葉細胞などの生殖系列細胞の培養技術法の確立や、遺伝導入法の開発を行っています。
発生工学研究チームでは、ブタを対象として、卵子や胚の体外受精や体外培養系の確立、体細胞クローン技術を利用した医療福祉に貢献する臓器移植や再生医療用ブタの開発に精力的に取り組んでいます。また、遺伝子改変ブタを作出するのに必要なベクターなどの基本的なコンストラクションや体細胞への相同組換え法の開発にも着手しています。
生殖再生研究チームでは、ウシにおける着床機序を解明するため、胎盤の機能に焦点を当てています。これまでに、妊娠経過に伴う各種生理活性部質の動態と遺伝子発現、子宮・胎盤葉細胞構造体や胚盤胞栄養膜細胞の3次元培養法の確立と、それらの遺伝子発現解析を進めています。また、卵胞発育・退行の過程に関連する遺伝子のcDNAマイクロアレーによる網羅的解析も行っています。
以上が家畜の分野ですが、個体再生能を高度に持つイトヒメミミズ新生細胞の遺伝子発現プロファイル、トランスポゾンPiggyBacを利用した形質転換カブラハバチをモデルとする性決定機構が発生機構研究チームで行われています。また、昆虫の脱皮ホルモンと幼若ホルモンの活性調節と情報伝達機構の解明が成長制御研究チームで進められています。
■おわりに
研究概要でも明らかなように、当グループの研究目的は、生命現象の開始点とも言える生殖細胞が持つ能力、受精、分化、器官形成に関与する遺伝子とその発現の基本原則を見つけることが使命と考えています。
研究する上で、基礎研究と技術開発研究のバランスも大事です。しかし、基礎研究だけで研究費がまかなえるほど国は太っ腹ではありません。事実、当グループの研究予算に占める交付金研究費(自由な発想を保証する)は15%以下で、自ら提案して獲得したプロジェクト研究の上に運営が成り立っています。
法人化になってからの利点は、海外出張が予算費目に縛られることなく自由になったこと、所独自の海外留学制度やポスドク制度が発足したことなどです。生物研ではポスドク経験者を採用の基本としています。多くの有能な若い方々に来て頂き、ともに研究をし、将来へ飛翔できる場を提供したいと考えます。
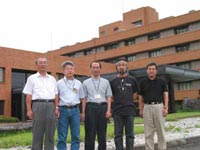 発生分化研究チーム長 |
 池の台地区案内板 |
This site has been maintained by the JSAR Public Affairs Committee.
Copyright![]() 1999-2003
by the Japanese Society of Animal Reproduction
1999-2003
by the Japanese Society of Animal Reproduction